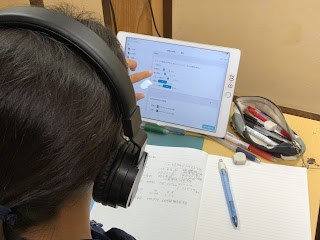「志望大の過去問を解く。反復する」から始める
高2も、夏休みに入るころは数ⅡBもほとんど習い、共通テストや国立大2次試験も、解説が読めるようになります。
- ハイスコア!共通テスト攻略数学I・A、Ⅱ・B(Z会 新装版7月発刊予定)
- 2022年共通テスト過去問研究I・A/Ⅱ・B 980円+税 教学社
を用いて、受験勉強を始める時期です。共通テスト過去問研究I・A/Ⅱ・Bには、32回分の過去問などを収載します。熊本大、広島大レベルを目指す人たちは、他教科も含めてこのシリーズを分冊して取り組むことが多いです。
2017年、当時高2の青雲高Yさんは、さらに
- 理系数学入試の核心(Z会) 2巡完成
- 数Ⅲの積分計算が面白いほどわかる本(KADOKAWA) 2巡完成
- チャート式医学部入試数学(数研) 高34月〜
で、全国の医学部の問題を九州の国立大過去問から1週間に1大学のペースで解き進め、Yさんはその後、東大模試で校内1位になりました。
長崎西高2Sさんは、通塾のたびに九大の赤本を1年分ずつ解きました。1問解いては解説を読んでチェックしたり、本番と同じ時間で取り組んだりしながら、まずは赤本5年分を解き上げました。
私が教える場面は、ホンのわずかです。彼らはずっと自分自身と向き合っています。問題を通して、大学が求めている人材像と今の自分の間合いを測っているのです。大学が要求する水準を実感することが、第1志望大学を目指す第1歩です。
学力を上げるには、「周回学習法」しかない
「わかる」「できる」
- 「わかる」 とは、説明できるか、で
- 「できる」 とは、再現できるか、で測定できます。
「できる」は反復で得られる能力です。
「勉強法を検討すべきだった」と反省。
広島大医学部に進学した長崎東高Kさんは高2から高3にかけて東大入試向けの問題集を解き進めていました。彼女は県トップクラスの成績。膨大な時間とエネルギーを「1問」に注ぎ込みます。しかしなかなか進みません。
解説を読めば十分理解できます。合否判定がA,B判定だと、ある程度解けるはず、と期待します。でも実は志望大専用の過去問の切り込み方を勉強しなければ解けないのですね。自力でどこまで解けるか、こだわらせ過ぎたのでした。<.p>
「7回読み勉強法」 山口真由さん
そんなとき、山口真由さんの「7回読み勉強法」に出会いました。次年度、同じく長崎東高から東大を目指すMくんには、この本にヒントを得て、一巡めの学習の「垣根」を下げて勉強させました。
以下「7回読み勉強法」から参考にした箇所の抜粋です。
- 最初に問題集を解くときには、問題形式にも慣れていないし、知識もないのだから、間違えるのは当たり前。どう考えても、間違える問題のほうが多いのです。ここでいちいち間違いと向き合っていると、気持ちが沈み、勉強がはかどりません。だからこの段階で間違った問題にチェックを入れることは一切しません。
- 自分の出した答えが違ったとしても、自分の回答のどこがどう違うのか、なぜ間違ったのか、などという分析は一切しませんでした。ただ、正答に付された解説を読むだけ。こうすると、自分の間違った考えにとらわれることなく、正答とその解説だけが記憶に残りやすくなります。
-
誤答のチェックをするのは、全問題を少なくとも5回以上解いたあと。その時点になると、全体的な理解も進んでいて、正答のほうが多くなっています。
-
正答率8割、誤答率2割くらいになってから、自分の間違った問題について分析するというのが、もっとも効率的なのでないかと思います。
長崎東高Mくんは「東大数学で1点でも多く取る方法 」(安田享さん著 これは名著です!)を高2の12月(2016)から解き始めて約60題を高3の高総体ごろまで半年かけて一巡めを解き上げました。2巡め、3巡めも順調に進み、一日に2問程度づつ確認テストをしながら高3の10月までに5巡したのです。これは私にとっても貴重な経験になりました。
そして次のような指導を試みました。
- 生徒が「わかった」と判断したことを私がさらに説明はしない。
- 周回してテストで確認すれば済むことである。
- 生徒の疑問が解決しないときに、ともに考え、理解を深める手助けをすればいい。
- 生徒が、自分が目標を見失わないように、学習スピードを落とさないように、状態を把握し支えることはもっと大事。
この指導で劇的な逆転を達成する生徒が出るようになりました。
補足
長崎東高卒、現広島大医学部在学中のKさんは、4月から夏までの河合塾での浪人生活をこう語っている。
「数学の先生から言われて、塾生向けの数学基本事項集を3巡したんです。すると成績がイッキに上がって東大医学部も狙える学力になりました。現役のときは難しい問題ばかり解いて基本が抜けていたんですね」
高校生の教科書と重複する点も多く、この教材にあって市販の受験参考書にはない、というものはありません。つまり、現役高校生でも、評価が高い受験参考書をきっちりと勉強することで十分カバーできるのです。
問題集選択の基準は、「6割、最低5割は自力で解ける。解説は7,8割はほぼ理解できる」。
問題集の評価はインターネットで検索するとわかります。でも、手に取って、自分にとって難しすぎないかはチェックしたほうがいい。
わたしは対象生徒にどう解かせるかイメージできる書籍しか推薦しません。「6割、最低5割は自力で解ける。解説は7,8割はほぼ理解できる」。問題集を選択することを勧めます。
問題集の一単元だけを取り組むことも「あり」かもしれませんが、わたくしは問題集のすべてをやり遂げ、それを周回することを高校生に期待しています。なぜなら、著者、編集者は何を学ばせるかという視点で問題を選び、解説しているからです。
高校生は「青春」をかけて問題集に取り組んでいます。彼らの時間を無駄にしないために、わたしはホンモノ=大学入試過去問しか教材にしかしません。学び尽くせる「1問」を徹底的に解きこむ。それが強の面白さと出会うきっかけになると考えています。
2017.4の記事を2021.7の現状に合わせ改編。